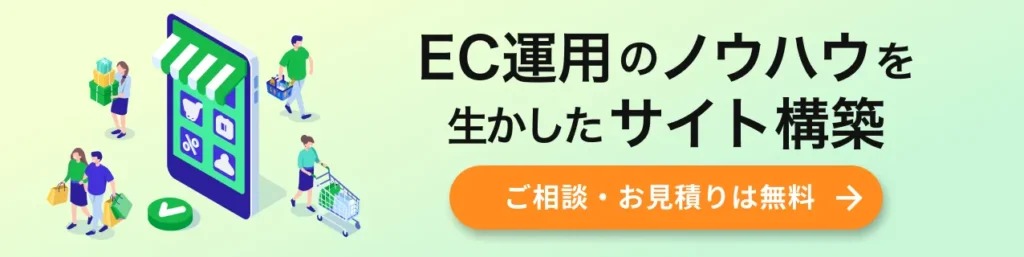Column
SEO対策は意味ないと感じてしまう理由を解決方法と一緒にご紹介!

いつもお世話になっております。
株式会社ベリッシマです。
今回の記事では、せっかくリソースを割いたSEO対策が「意味ない」と感じてしまう理由と、その解決方法をご紹介させていただきます。
一度諦めていたSEO対策によるアクセス数増加を再度目指したい企業様・事業主様はぜひ参考にしてみてください。
また、この記事で分からないことがありましたら、当サイトのコンタクトフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お見積りは無料です。
まずは「SEO対策は意味ない?」に対しての結論から。
目次
問:SEO対策は意味ない? 答:意味はあります!!
まずは結論からですが、SEO対策は『意味があります』。
前提としてのそもそも論ですが、もしSEO対策に意味がないのであれば、SEOの専門業者は食いっぱぐれますし、多くの人が鎬を削って検索順位を競う必要はない訳です。
ではなぜ、多くの人が「SEO対策は意味ない」と感じてしまうのでしょうか。
次項より、その理由を順番に解説します。
SEO対策は意味ないと感じる理由1:短期的な効果が見えにくい
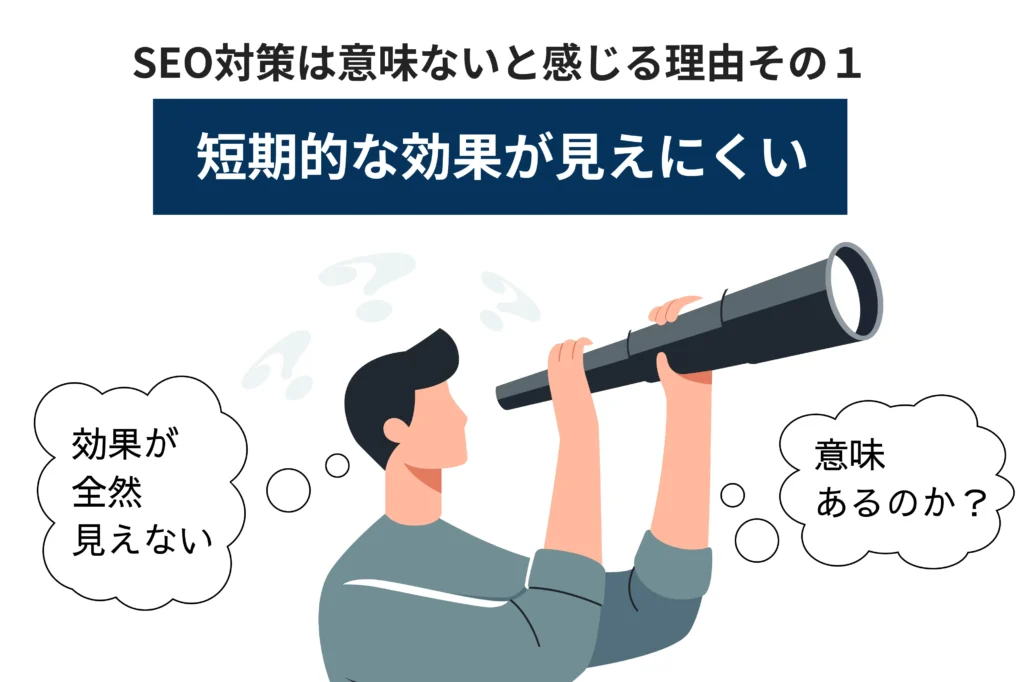
SEO対策は即効性がある施策ではなく、効果が現れて実感できるまでには数週間・数ヶ月、場合によっては1年以上かかることがあります。
SEO対策を施したからと言って「明日には検索順位が上がってアクセス数も増える」なんてことはほぼあり得ないことは念頭に置いて、長期的な視点でSEO対策に取り組む姿勢が大切になります。
解決方法
- 長期的な視点を持ち、最低でも数ヶ月は継続して取り組むようにする
- 定期的に効果を測定・進捗を確認し、小さな改善点を見つける視座を持つ
長期的な視点を持ち、最低でも数ヶ月は継続して取り組むようにする
SEO対策は、すぐに結果が出るものではなく、じっくりと時間をかけて取り組む必要があります。
短期間で順位が上がらないからといって諦めてしまうのではなく、少なくとも数ヶ月は継続して対策を続けることが重要です。
なぜなら、検索エンジンのアルゴリズムは複雑で、Webサイトの変更やコンテンツの追加などが評価されるまでに時間がかかるからです。
また、競合サイトも日々対策を行っているため、一時的に順位が上がっても、すぐに下がることもあります。
長期的な視点を持ち、コンテンツの質を高めたり、サイトの構造を改善するなど、地道な努力を続けることが成功への鍵となります。
定期的に効果を測定・進捗を確認し、小さな改善点を見つける視座を持つ
SEO対策は、ただ闇雲に行うだけでは効果は期待できません。
定期的に定量的な効果測定を行い、自社サイトの現状を把握することが不可欠です。
アクセス数や検索順位、コンバージョン率などを定期的にチェックし、どの施策がうまくいっているのか、どこに改善の余地があるのかを分析します。
そして、分析結果に基づいて、小さな改善点を積み重ねていくことが大切です。
例えば、特定のキーワードでの順位が低い場合は、コンテンツをリライトしたり、内部リンクを強化したりすることで改善を図ります。
また、ユーザーの検索意図に合わないコンテンツは、修正または削除することも検討しましょう。
小さな改善を繰り返すことで、徐々にSEOの効果を高めていくことができます。
個人的に「継続は力」が最も似合う施策がSEO対策だなと思っているほど、SEO対策には即効性はなく忍耐が必要になります。
その分、結果が出始めると面白いほどアクセス数が増え、しかも継続的な流入が見込めるのがSEOの良いところです。
例外:サイトの運用歴が長いと結果に即効性がある場合もある
これは弊社がSEO対策を担当させていただいている企業様での実例ですが、サイトの運用歴が長い場合は歴に応じたドメインパワーが蓄積されているので、そういったサイトへのSEO対策実施は比較的早い段階から効果を実感できるケースも多いと感じています。
「サイトの運用歴は長いけど一向にアクセスは増えない…」
と感じている担当者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。
もちろんご相談・お見積りは無料です。
SEO対策は意味ないと感じる理由2:アクセス数が増えても成果に結びつかない
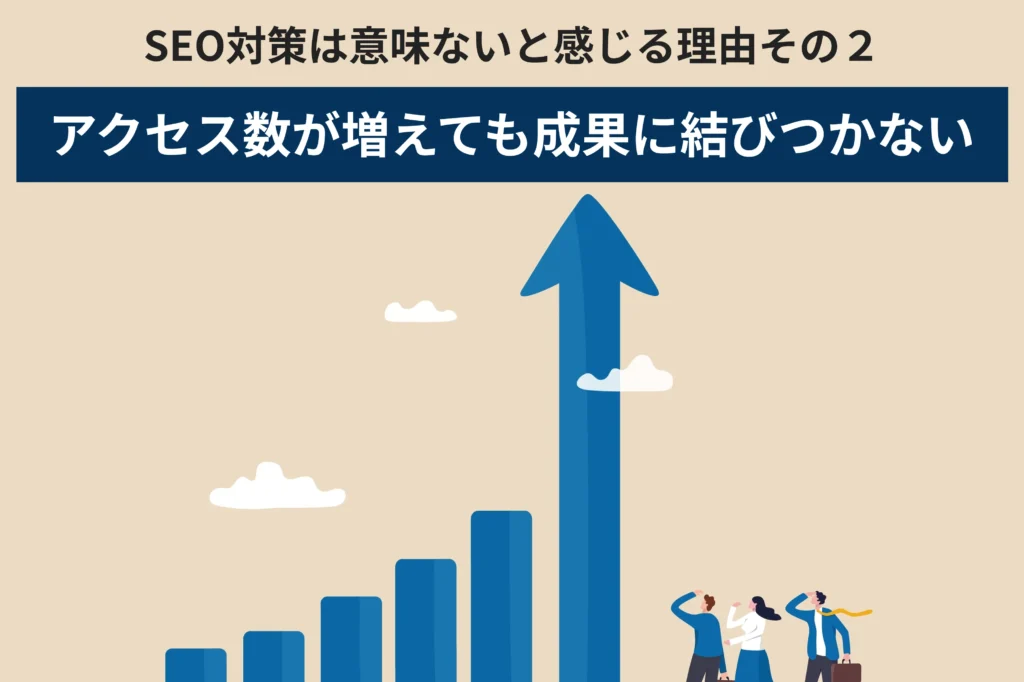
アクセス数が増えてもコンバージョンや売上につながらないことがあるので「SEO対策は意味がない」と感じてしまうケースもあります。
アクセス数の増加とコンバージョンの増加はイコールではないことを念頭に置いてSEO対策に取り組むことが大切です。
解決方法
- ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを作成する
- コンバージョン最適化(CRO)も並行して行う
ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを作成する
SEO対策でコンバージョン成果を出すためには、「ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを作成する」ことが不可欠です。
検索エンジンは、単にキーワードが含まれているページよりも、ユーザーが本当に求めている情報を的確に提供するページを高く評価します。
ユーザーが検索する際には、何らかの悩みや疑問、目的があり、その解決策や答えを探しています。
したがって、コンテンツを作成する際は、ターゲットとなるユーザーがどのような意図で検索しているのかを深く理解し、そのニーズに応える情報を提供することが重要です。
また、検索意図に合致したコンテンツは、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、サイトへの滞在時間や回遊率の向上にもつながります。
これらのユーザー行動は、検索エンジンからの評価にも直結し、結果的に検索順位の向上が期待できます。
さらに、検索意図を正確に捉えるためには、検索キーワードの裏にあるユーザー心理や、関連する悩み・課題まで掘り下げることが重要です。
実際のユーザーの声やアクセス解析データを活用し、どのような情報が求められているのかを常に検証・改善していく姿勢が求められます。
こうしたプロセスを経て作成されたコンテンツは、ユーザーにとって価値ある情報源となり、長期的な成果につながります。
コンバージョン最適化(CRO)も並行して行う
SEO対策によってアクセス数が増えても、最終的な成果であるお問い合わせや購入といった「コンバージョン」に結びつかなければ、ビジネスの成長にはつながりません。
そのため、SEOと並行して「コンバージョン最適化(CRO)」にも取り組むことが重要です。
CROとは、サイトに訪れたユーザーが目的のアクション(例:問い合わせ、資料請求、購入など)をスムーズに行えるように、サイトやページの構成・導線・デザイン・コンテンツを最適化する施策です。
具体的には、ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けるように、ページのレイアウトやボタンの配置、フォームの入力項目の見直しなどを行います。
また、ユーザーが行動を起こしやすくするための訴求ポイントや、信頼感を高める要素(例:実績紹介、口コミ、FAQなど)を充実させることも効果的です。
SEOによって集客したユーザーが、サイト内で満足し、最終的な成果につながるように導線を整えることがCROの目的です。
CROを実施することで、同じアクセス数でもコンバージョン率が向上し、より高い成果を得ることができます。
SEOとCROは別々の施策ではなく、両輪として機能させることで初めてWebサイトの価値を最大化できます。
アクセス数の増加だけで満足せず、ユーザーの行動データを分析し、どこで離脱が多いのか、どのページが成果に結びついているのかを把握し、継続的に改善を重ねることが重要です。
こうした取り組みが、SEO対策の「意味」を最大限に引き出し、ビジネス成果へとつなげる鍵となります。
SEO対策は意味ないと感じる理由3:適切なキーワード選定ができていない
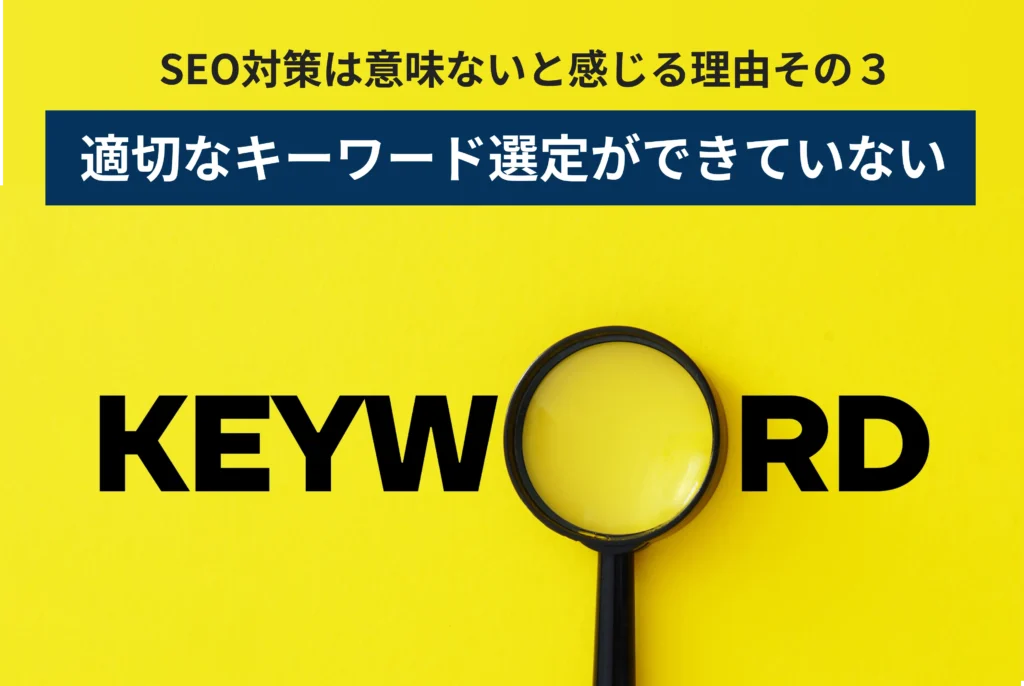
SEO対策にキーワードの選定は意味がないと感じている方も多いと思います。
キーワードをしっかり選んだにも関わらず効果が感じられない場合、サイトに訪れてほしいターゲットとするユーザーが検索するキーワードや、自社の商品・サービスに関連するキーワードを適切に選定できていない可能性が非常に高いと言えます。
そういった結果だと、SEO対策としては不適切な施策になってしまうので、結果的に効果を得ることは難しいでしょう。
しかし、長年のSEO対策の経験から個人的な見解を述べさせていただくと、キーワード選定を間違わなければSEOにおいて比較的効果がわかりやすい要因の一つだと私は思います。
解決方法
- キーワード調査ツールを活用して選定する
- ユーザーの検索意図を理解し、適切なキーワードを選定する
SEO対策は意味ないと感じる理由4:サイト構造や内部リンクの最適化が不十分
サイト構造や内部リンクの最適化は、SEO対策において非常に重要な要素ですが、その重要性が見過ごされがちです。
適切に設計されたサイト構造は、ユーザーにとって情報を見つけやすくするだけでなく、検索エンジンのクローラーにとっても各ページの関連性や重要度を理解しやすくします。
しかし、多くのウェブサイトでは、この点が軽視されがちです。
不適切なサイト構造では、重要なページが深い階層に埋もれてしまったり、関連コンテンツ同士のつながりが弱くなったりします。
これにより、ユーザーが目的のページにたどり着くまでに時間がかかり、結果として離脱率が上がってしまいます。
また、検索エンジンのクローラーも各ページの重要度を正確に判断できず、適切なランキングを付けられなくなります。
内部リンクについても同様です。
効果的な内部リンク戦略がない場合、サイト内の重要なページへの導線が弱くなり、ページ間の関連性も低下します。
これは「リンクジュース」と呼ばれるSEO上の価値が適切に分配されないことを意味し、結果としてサイト全体のSEO効果を低下させてしまいます。
さらに、不適切なサイト構造や内部リンクは、新しいコンテンツを追加する際の障害にもなります。
体系的な構造がないと、新規ページをどこに配置すべきか判断が難しくなり、結果として整理されていないカオス状態のサイトになってしまう可能性があります。
これらの問題により、SEO対策を行っているにもかかわらず、期待した効果が得られないという状況に陥ることがあるため、「SEO対策は意味がない」と感じてしまう原因の一つとなっているのです。
解決方法
- サイトマップの作成と最適化
- 内部リンク戦略の見直し
- パンくずリストの実装
- カテゴリーページの強化
- 定期的な構造の見直し
次項より解説いたします。
サイトマップの作成と最適化
サイトマップは、Webサイト全体の構造を視覚的に表現したもので、ユーザーと検索エンジンの両方にとって重要な役割を果たします。
ユーザーにとっては、サイト内の情報を見つけやすくするナビゲーションの役割を果たし、検索エンジンにとっては、サイト全体の構造を理解し、効率的にクロールするための手助けとなります。
サイトマップを作成する際には、まず、Webサイトのすべてのページをリストアップします。
次に、ページ間の階層構造を明確にし、サイトマップに反映させます。
理想的なサイト構造は、トップページから3クリック以内にすべてのページにアクセスできるような、浅く広い構造です。
サイトマップは、HTML形式とXML形式の2種類があります。
HTML形式のサイトマップは、ユーザー向けにWebサイト上に公開します。
XML形式のサイトマップは、Google Search Consoleなどの検索エンジンに送信し、クローリングを促進します。
サイトマップは、定期的に更新し、Webサイトの最新の状態を反映するようにしましょう。
内部リンク戦略の見直し
内部リンクは、Webサイト内のページ同士を結びつけるリンクのことです。
内部リンクを効果的に活用することで、ユーザーの回遊性を高め、SEO効果を向上させることができます。
内部リンク戦略を見直す際には、まず、Webサイト内の重要なページを特定します。
次に、関連性の高いコンテンツ同士を適切にリンクさせます。
特に、キーワードを含むアンカーテキストを使用して内部リンクを張ることで、そのページの主題を検索エンジンに明確に伝えることができます。
ただし、過剰な内部リンクは、SEO効果を低下させる可能性があるため、注意が必要です。
内部リンクは、自然な流れで、必要な箇所に適切に配置するように心がけましょう。
内部リンクは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって有益なものでなければなりません。
パンくずリストの実装
パンくずリストは、Webサイトの各ページに表示される現在位置を示すナビゲーションです。
パンくずリストを実装することで、ユーザーは現在どのページにいるのかを容易に把握でき、上位階層への移動もスムーズに行えます。
これは、ユーザビリティを向上させるだけでなく、検索エンジンにもサイト構造を明確に伝えることができます。
パンくずリストは、通常、トップページから現在のページまでのパスを表示します。
各階層へのリンクが含まれており、クリックすることで上位階層へ移動できます。
パンくずリストは、Webサイトのすべてのページに実装することが推奨されます。
適切なパンくずリストは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって価値のあるものです。
カテゴリーページの強化
カテゴリーページは、Webサイト内のコンテンツをテーマごとに整理しグループ化するための重要なページです。
カテゴリーページを強化することで、ユーザーは目的の情報を見つけやすくなり、検索エンジンはサイト構造を理解しやすくなります。
カテゴリーページには、カテゴリーの説明文を追加し、そのカテゴリーに属する記事へのリンクを適切に配置します。
説明文は、カテゴリーの内容を簡潔にまとめ、キーワードを含めることが望ましいです。
リンクは、関連性の高い記事を優先的に配置し、ユーザーが興味を持つ可能性の高い記事を強調します。
適切に強化されたカテゴリーページは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって価値のあるものです。
定期的な構造の見直し
Webサイトは、時間とともに成長し、変化していきます。
新しいコンテンツが追加されたり、ビジネスの方向性が変わったりすることもあります。
そのため、Webサイトの構造は、定期的に見直し、必要に応じて再編成することが重要です。
構造の見直しでは、まず、サイトの現状を評価します。
アクセス解析のデータを分析し、ユーザーの行動を把握します。
ユーザーが目的の情報を見つけられているか、どのページで離脱しているかなどを確認します。
次に、評価結果を基に、構造の改善点を特定します。
不必要に深い階層や孤立したページがないか、カテゴリー分けが適切かなどを見直します。
最後に、特定された改善点を実施し、Webサイトの構造を最適化します。
定期的な構造の見直しは、WebサイトのユーザビリティとSEO効果を維持するために不可欠です。
ドメインパワーは意味ない?
SEO対策の効果に有効と言われるドメインパワーですが、まずはドメインパワーについておさらい。
ドメインパワーとは
ドメインパワーとは、Webサイトの信頼性や権威性を示す指標で、SEO対策において重要な要素です。
通常、0から100のスコアで表され、数値が高いほど検索エンジンからの評価が高くなります。
この指標はGoogleの公式な評価ではなく、SEOツール開発会社が独自に算出したものです。
ドメインパワーが高いサイトは、検索結果で上位表示されやすく、新しいコンテンツも早期にインデックスされる傾向があります。
その向上には、質の高い被リンクの獲得や長期的な運用、ユーザー満足度の向上などが必要です。
競合が多いキーワードで優位に立つためにも、ドメインパワーの強化は欠かせません。
つまり、当然ですがドメインパワーは低いより強い方がSEO的には何かと有利ということになります。
ドメインパワーを強化するには
ドメインパワーを上げる具体的な対策としては以下の方法が挙げられます。
- 高品質なコンテンツの作成
- 被リンクの獲得
- 内部リンクの最適化
- サイト構造の改善
- 質の低いリンクやコンテンツの改善
- 定期的な更新
上記を順に解説します。
高品質なコンテンツの作成
SEOにおいて高品質なコンテンツは、検索エンジンからの評価とユーザー満足度を同時に高める基盤です。
単にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーが求める課題解決や情報ニーズに応える「検索意図」を徹底的に分析し、専門性・信頼性・網羅性を兼ね備えた内容が求められます。
例えば、製品比較記事では客観的なデータと体験者の声を組み合わせ、医療情報なら最新の研究結果や専門家の監修を明記します。
GoogleのE-E-A-T(専門性・実績・権威性・信頼性)基準を意識し、競合が提供できない独自の洞察や具体的事例を盛り込むことで、検索順位の向上とコンバージョン率の改善を両立できます。
特に、動画やインフォグラフィックを活用したマルチフォーマット展開は、ユーザーの理解深化と滞在時間延長に効果的です。
コンテンツの品質基準は年々厳格化しており、継続的なオリジナル性の追求が必要不可欠になります。
被リンクの獲得
被リンクは検索エンジンがサイトの権威性を測る重要指標の一つです。
質の高い被リンクを獲得するには、ニュース性のあるプレスリリースの配信や業界専門メディアへの寄稿など、能動的な情報発信戦略が必要です。
例えば、自社の調査データをパブリッシャー向けにパッケージ化し、メディア関係者に提供する「データジャーナリズム」手法は、自然な被リンク獲得に有効です。
地域密着型ビジネスでは地元メディアや自治体サイトからの被リンクが重要で、コミュニティイベントの共催や社会貢献活動の可視化が効果的です。
被リンク獲得は時間を要しますが、持続的なトラフィック増加とブランド認知向上の両面で長期投資価値が高い施策となっております。
内部リンクの最適化
内部リンク戦略は、検索エンジンのクローラビリティ向上とユーザーの回遊促進を同時に実現する技術です。
重要なページに対してはトップページからの直リンクを配置し、関連コンテンツ間では文脈に即した自然なアンカーテキストを使用します。
例えば、商品ページから「よくある質問」セクションへ、ブログ記事からカテゴリーページへと、ユーザーの興味に沿った導線を設計します。
内部リンクの最適化には、XMLサイトマップの更新頻度管理やcanonicalタグの適切な使用も含まれ、大規模サイトではリンクエクイティの偏りを防ぐための定期的なチェックが欠かせません。
また、モバイル版とデスクトップ版でリンク構造が異なる場合の対応や、JavaScriptベースのリンクの扱いなど、技術的な側面への配慮も重要です。
サイト構造の改善
検索エンジンがサイトを効率的にクロールできるよう、論理的な階層構造とシンプルなURL設計が求められます。
理想的な構造は、トップページから3クリック以内で全ページにアクセス可能な「浅く広いツリー型」で、カテゴリー分けはユーザーの検索行動データに基づいて設計します。
例えば、ECサイトでは「商品カテゴリー>サブカテゴリー>商品詳細」という階層に加え、ユーザー属性別(例:初心者向け/プロ向け)や季節別のナビゲーションを追加すると効果的です。
大規模サイトでは、動的ファセットナビゲーションの最適化や、オーバーセグメンテーション(過剰な細分化)を防ぐためのカテゴリー統合が重要になります。
サイト構造改善後は、リダイレクトチェーンや孤立ページの解消、クロールバジェットの最適化を通じて、検索エンジンの評価効率を最大化します。
特に、XMLサイトマップの自動生成システム導入や、JavaScriptフレームワーク使用時のプリレンダリング対策は、現代的なSEOに不可欠な要素です。
質の低いリンクやコンテンツの改善
SEO評価を低下させる低品質要素の排除は、リスク管理と評価効率化の観点から必須作業です。
リンク面では、過剰な相互リンクやアンカーテキストの不自然な偏りを是正します。
コンテンツ面では、薄いコンテンツ(シャローコンテンツ)や重複ページを特定し、オリジナル性の低い記事についてはリライトまたはnoindexタグで対処します。
特に、ユーザー離脱率が高いページや直帰率90%超のページは、コンテンツの根本的な改善が必要となります。
定期的な更新
SEOの持続的効果を得るには、コンテンツの鮮度管理と技術的なメンテナンスを継続的に実施する必要があります。
季節性コンテンツは前倒しで更新し、統計データを含む記事は毎年数値を見直すなどの対応が必要になります。
技術面では、Core Web Vitalsの基準達成状況を月次チェックし、モバイル表示の最適化やAMP対応の見直しを行います。
特に、Googleアルゴリズムアップデート(例:コアアップデートやスパムアップデート)が発表された際は、直近3ヶ月のアクセス変動を分析し、必要に応じてコンテンツ戦略を調整します。
更新作業では、ユーザー行動データ(ヒートマップ分析やセッション記録)を活用し、離脱ポイントの改善やCTA配置の最適化を実施します。
さらに、構造化データの拡充やサイトのHTTPS化徹底、EUのGDPR対応など、法規制や技術基準の変化にも柔軟に対応することが、長期的なSEO成功の鍵となります。
ドメインパワーが強いサイトへのSEO対策の成功事例
手前味噌で恐縮ですが、弊社がSEO対策を対応させていただきました小売業者様のECサイトのSEO対策成功事例をご紹介させていただけます。
以下の効果は全て昨対での同月間比較データです。
- 月間セッション数が 57.75%(5,000pv強)アップ
- 月間CTRを 1.3%改善
- 月間検索順位を平均約4位アップ
上記データはECサイトの運営歴が長いサイトへSEO対策に着手して初月のデータになっております。
お客様が運営されているサイト自体のポテンシャルが高い場合は初月から効果が出ることもありますので、自社のコーポレートサイト・ECサイトの運営歴が長い事業者様はSEO対策の効果を早い段階で実感できる可能性が高いと言えます。
ご相談・お見積りは無料は無料ですので、気になる事業者様はぜひお問い合わせいただけますと幸いです。
まとめ:適切なSEO対策はアクセス数を増やします!
ということで今回は、SEO対策は意味ないと感じてしまう理由と解決方法をご紹介させていただきました。
SEO対策は長期的な視点と意味のある施策をすることによって効果を得ることができます。
ホームページのSEOについてご不明な点がありあしたら、ご相談・お見積りは無料ですので弊社までお気軽にご連絡いただけますと幸いです。(弊社の制作実績もぜひ参考にしていただければ幸いです。)
弊社のコンタクトフォームはこちら👈